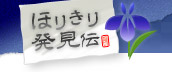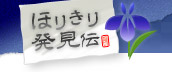「印傳」とは、古来インド(印度)より伝えられた技術であることから、その名がつけられたようです。鹿革にインドの更紗模様の型紙で色染めしたものが一般的なデザインです。鹿の皮は柔らかく、また強度も十分なことから、昔は武具の一部として鎧や兜に使われ武将など多くの日本人に愛用されていました。
時代を経るにつれて皮の表面にうるし加工をほどこすようになり、防水性にも優れ更に色うるしを使うことでカラフルな庶民的な袋物として人気を集めました。印傳も現在その技術を持つ工房は日本でたった6軒、東京では「印傳矢部」のみなのです。 |